逆流性食道炎について
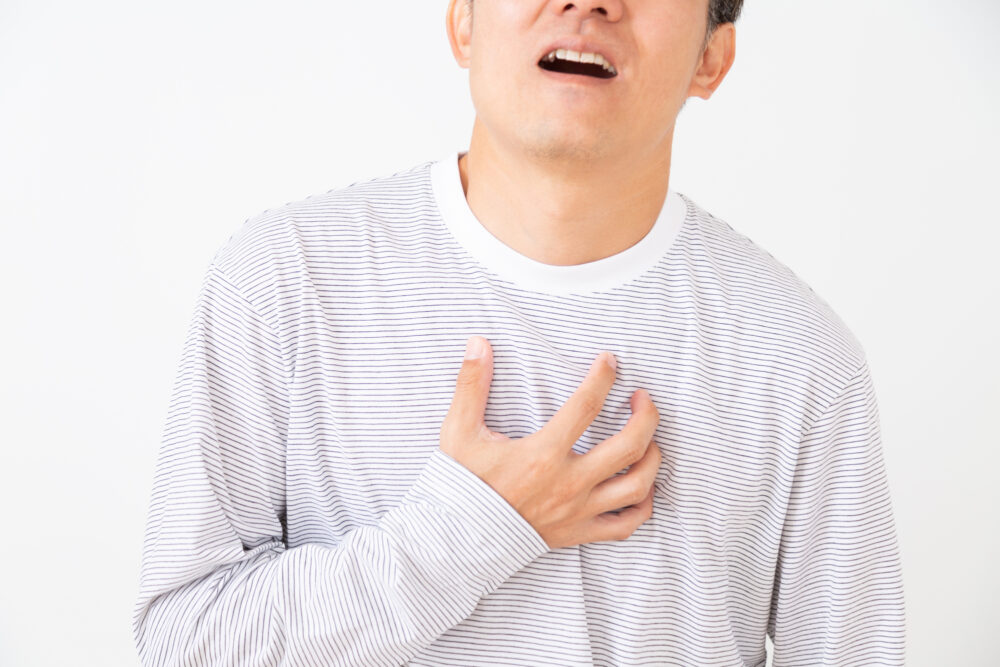 逆流性食道炎とは、何らかの理由で、下部食道括約筋という筋肉の機能が低下し、胃液が食道方向へと逆流することで、食道に炎症が起こり、慢性的に胸焼けなどの症状が起こる疾患です。逆流性食道炎は肉や脂っこい食べ物が多い食生活や、食べてすぐ横になるなどの生活習慣、肥満、飲酒などが関係して発症するとされています。
逆流性食道炎とは、何らかの理由で、下部食道括約筋という筋肉の機能が低下し、胃液が食道方向へと逆流することで、食道に炎症が起こり、慢性的に胸焼けなどの症状が起こる疾患です。逆流性食道炎は肉や脂っこい食べ物が多い食生活や、食べてすぐ横になるなどの生活習慣、肥満、飲酒などが関係して発症するとされています。
逆流性食道炎に
なりやすい方
逆流性食道炎が起こりやすくなる原因として、「裂孔ヘルニア」が挙げられます。食道裂孔ヘルニアとは、食道裂孔(食道が横隔膜を通過するための穴)から胃の一部が横隔膜の上へ飛び出している状態です。食道裂孔ヘルニアは、何らかの理由で腹圧が高まり、胃が押し上げられることで起こります。腹圧が上がる要因は、肥満や喫煙、腹水、妊娠、慢性的な咳などが挙げられます。また、生まれつき食道裂孔が緩い場合や、加齢によって食道裂孔が広がることで起こる場合もあります。
逆流性食道炎の症状
- 酸っぱいものが込み上げる感じがする(呑酸)
- のどがつかえた感じがする
- のどに違和感を覚える
- みぞおちや胸部に痛みを感じる
- 咳
- げっぷ
- 胸焼け
- かすれた声になる
- 胃のムカつきを感じる
など
逆流性食道炎の原因
 逆流性食道炎は、老化や肥満、食道裂孔ヘルニア、脂っこい食事・コーヒーの飲みすぎ・飲酒・喫煙などの生活習慣が原因となって起こると考えられています。
逆流性食道炎は、老化や肥満、食道裂孔ヘルニア、脂っこい食事・コーヒーの飲みすぎ・飲酒・喫煙などの生活習慣が原因となって起こると考えられています。
逆流性食道炎の診断・検査
逆流性食道炎の治療
逆流性食道炎の治療では、胸焼けや呑酸(酸っぱいものが上がってくる感じ)などの症状の緩和と、再発防止のための生活習慣の改善が重要です。症状の緩和では、胃酸の分泌を抑制する薬の処方を中心とした薬物療法を行います。生活習慣の改善では、食生活を中心とした生活習慣指導を行います。逆流性食道炎は、長期化すると、バレット食道やバレット食道がんなどを引き起こす疾患であるため、再発を繰り返さないように継続的に治療を行い、炎症を根本的に治していきましょう。
薬物療法
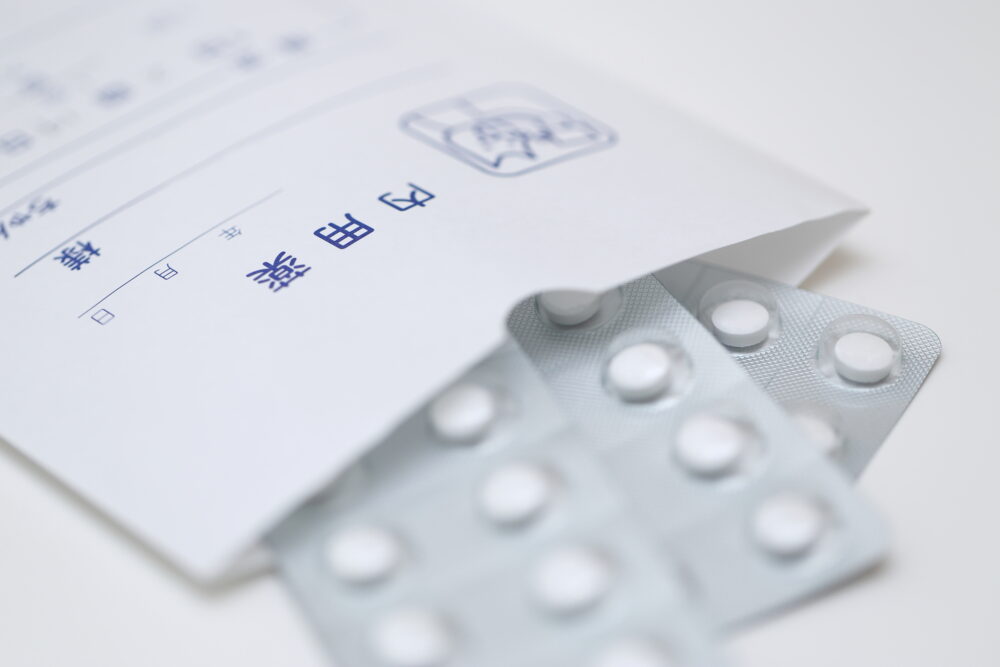 薬物療法では、主にプロトンポンプ阻害薬(PPI)という胃酸の分泌を抑える薬を処方します。プロトンポンプ阻害薬は、粘膜の炎症などの症状の緩和に効果が高いとされています。また、患者様の状態に合わせて、消化管運動を活発化させて、消化を促進する薬を処方する場合もあります。当院では、患者様の症状や生活習慣を丁寧にお聞きし、患者様に合わせた薬の処方を行っています。
薬物療法では、主にプロトンポンプ阻害薬(PPI)という胃酸の分泌を抑える薬を処方します。プロトンポンプ阻害薬は、粘膜の炎症などの症状の緩和に効果が高いとされています。また、患者様の状態に合わせて、消化管運動を活発化させて、消化を促進する薬を処方する場合もあります。当院では、患者様の症状や生活習慣を丁寧にお聞きし、患者様に合わせた薬の処方を行っています。
生活習慣改善
再発防止のためには、生活習慣改善が重要です。
食生活
栄養のバランスが取れた食事を1日3回決まった時間に食べるようにしましょう。また、ソーセージやハムなどの加工肉や肉料理、脂っこい食べ物、香辛料が多く含まれる食べ物は逆流性食道炎を悪化させる要因となるため、避けるようにしてください。食物繊維などを多めに食べるようにしましょう。
嗜好品
飲酒はアルコールが筋肉を緩め、下部食道括約筋の機能を低下させ、胃酸が食道へ逆流する要因となるため、特に就寝前の飲酒は避けるようにしてください。また、コーヒーも胃酸の逆流を誘発させる要因となるため、あまり飲み過ぎないようにしましょう。喫煙も逆流性食道炎の要因となるため、禁煙するようにしましょう。禁煙が困難な方は、病院が行う禁煙指導を利用すると良いでしょう。
睡眠
食後すぐに横になると、胃酸が食道へ逆流することがあるため、食後3時間程度は横にならないようにしましょう。また、胸焼けや咳の症状がつらい方は、上半身をやや起こした状態で睡眠を取ると、症状が軽くなることがあります。
腹圧
腹圧が高いと、胃が押され、胃酸が食道へ逆流することがあります。腹圧を高めないために、締め付けの強い衣類は避け、前かがみの姿勢や猫背は改善しましょう。便秘がある場合は便秘の改善も腹圧を下げる効果があります。また、肥満の方は、減量を行いましょう。
運動
水泳やウォーキングなどの軽い有酸素運動は、逆流性食道炎の症状の緩和効果があります。できるだけ習慣化すると良いでしょう。また、運動は便秘や肥満の改善効果もあります。










